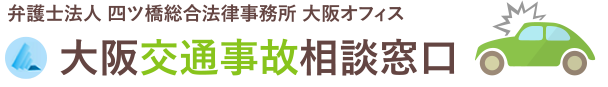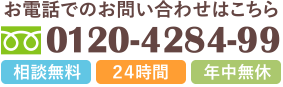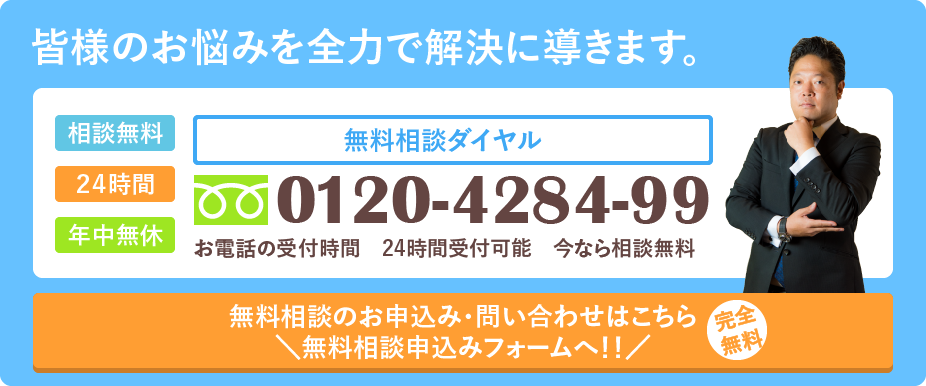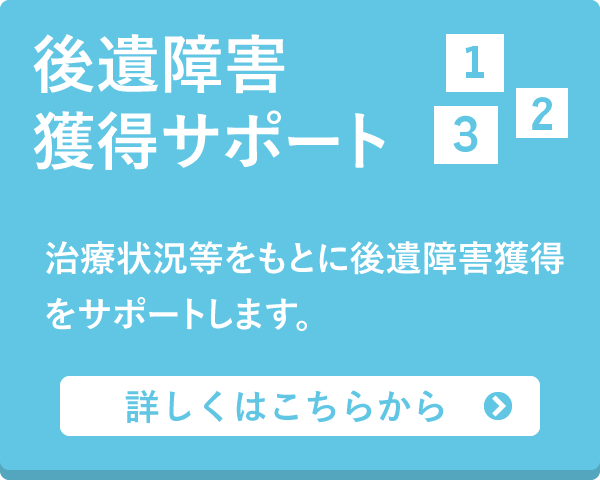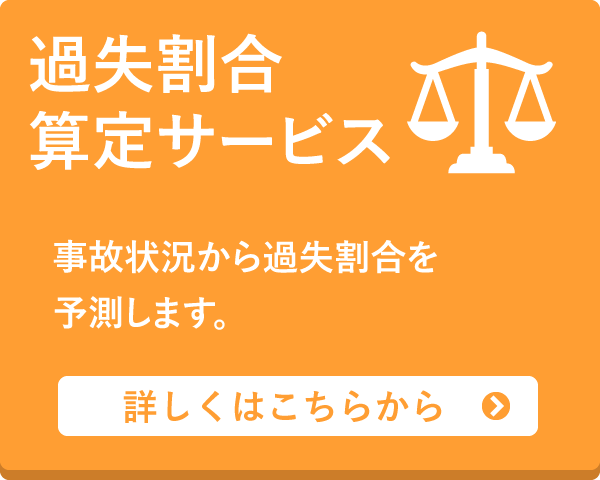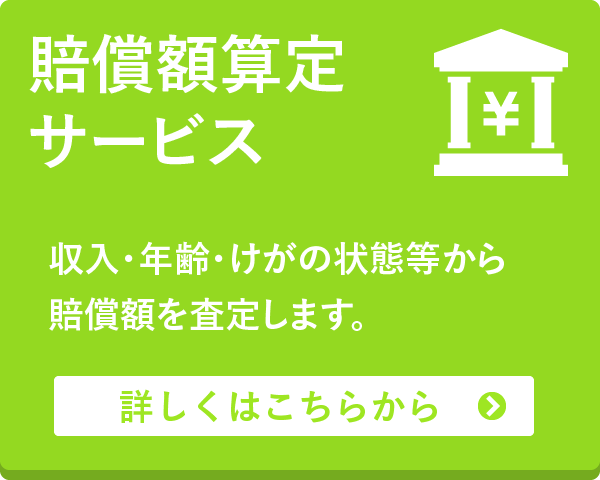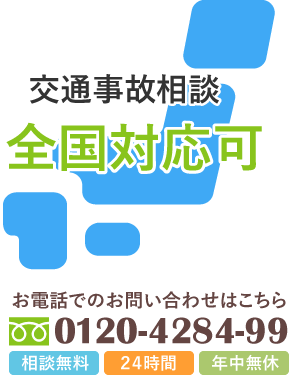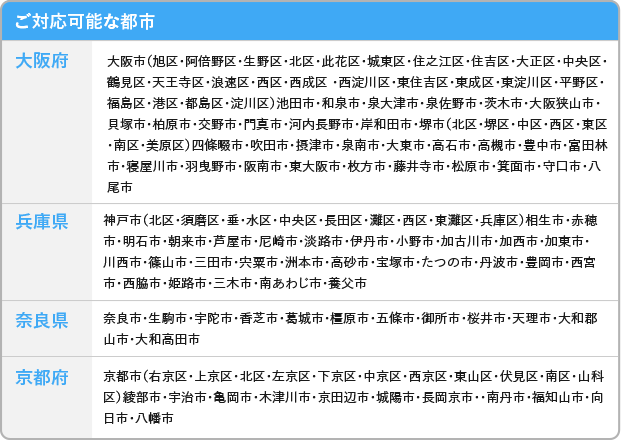交通事故における症状固定とは?
2017/01/18

この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

交通事故における症状固定とは?
交通事故に遭ったことで生じたケガや骨の変形・痛みなどが、「これ以上治療を継続しても改善が見込めない」と判断されることを症状固定と呼びます。
交通事故の場合は一般のケガなどと比べて症状固定に至るまでの期間やその後の取扱い、対処方法が全く異なりますので、これから紹介するポイントを頭に入れた上で各種手続きを進めることをお勧めします。
交通事故の症状固定は誰が決めるもの?
交通事故における症状固定は、検査や治療を行っていた担当医師の医学的な観点によって判断されるものです。
患者さんが「もっと治療を続ければ症状が改善する」と考えても、担当医師の判断がなければ更に通院を継続することはできないことがあります。
症状固定までに必要となる期間とは?
実際の交通事故被害の事例を確認すると、症状固定までにかかる期間がイメージしやすくなります。
《むち打ち症の場合》
むち打ち症は、症状固定までの期間が比較的短いといえます。
むち打ち症で後遺障害等級認定を受けるためには、最低6ヶ月以上の治療期間が必要になると言われています。
酷い玉突き事故に遭ったなどの場合は、1年以上の通院を要するケースも見受けられますので、半年を過ぎたからと言って無理に治療を終わらせる必要はないと言えるでしょう。
《骨折の場合》
骨折に関する後遺障害は、担当医師の判断も比較的行いやすいことから、長時間の治療を要せず症状固定するケースがほとんどです。
しかし骨折によってリハビリが必要となる場合は、治療期間も長くなることで6ヶ月以上が症状固定までにかかることが多いと考えて良いでしょう。
《醜状障害の場合》
人目に触れる部分に傷を負った醜状障害の場合は、傷が治ってから6ヶ月の経過を待たなければ症状固定の判断ができません。時間がたつと傷が収縮することがあります。
傷の長さで自賠責保険の金額が変化するので、6ヶ月経過時に症状固定させるべきといえます。
またレーザー治療によって傷跡の症状改善をする場合は、複数回の照射が必要となり治療期間が長くなることが予想されますので、症状固定の後に治療に臨むべきです。
まとめ
後遺障害等級認定のポイントとなる症状固定は、自賠責保険や任意保険から支払われる金額を決める上でも欠かせない要素となります。
長きに渡る通院が面倒になって治療を中断してしまうと、症状固定も当然できなくなるため注意が必要です。
今回紹介した症状固定を含めて交通事故トラブルでお困りのことがございましたら、後遺障害等級認定などにも詳しい当事務所にご相談ください。
交通事故
に強い