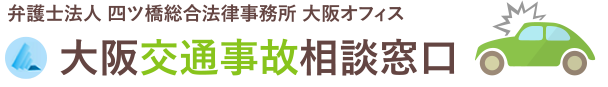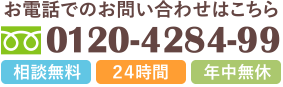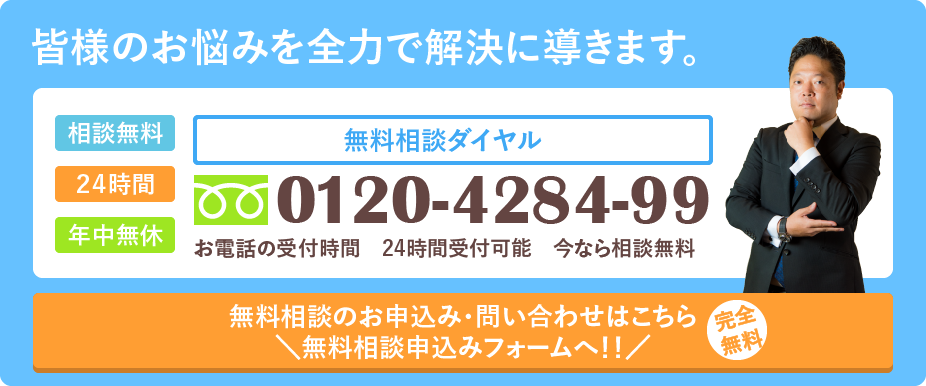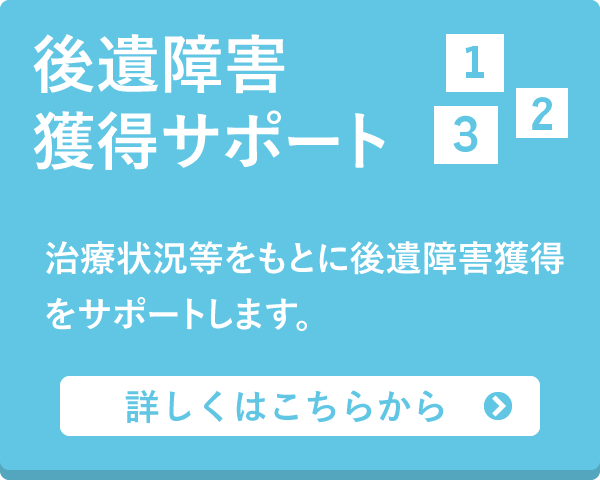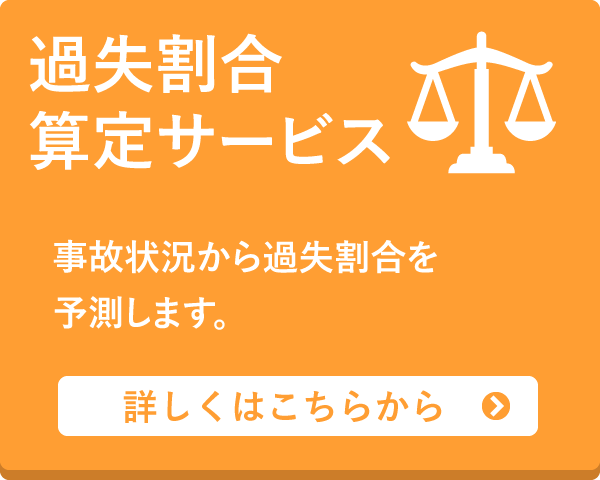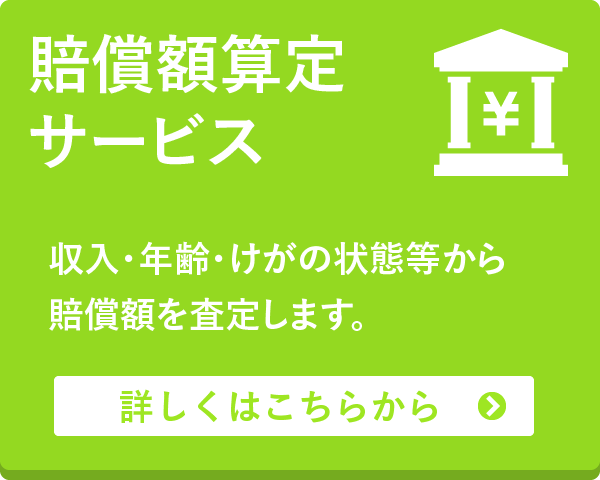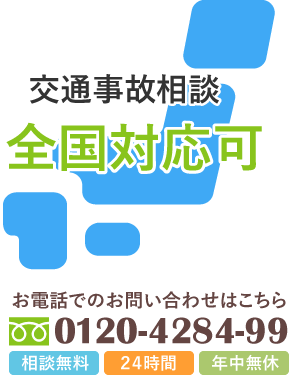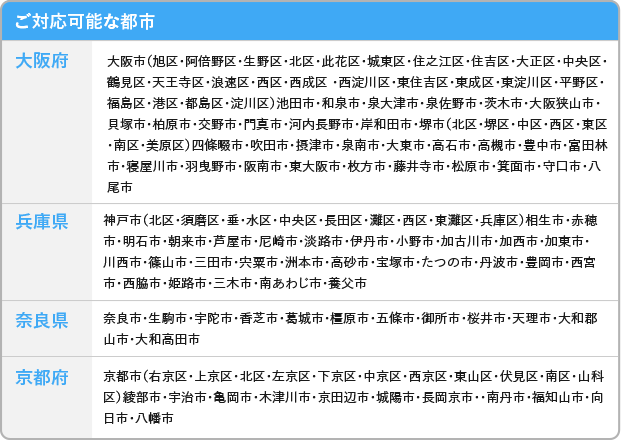早期釈放・不起訴になる!?飲酒運転で逮捕された後に弁護士を雇うメリットとは?
2018/04/19

この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

家族や友人知人といった身近な人が飲酒運転で逮捕されてしまった場合、刑罰の軽減と早期釈放を目指して、弁護士を雇うことも理想的な問題解決法のひとつと考えられています。
過去の判例などを見てみると、同じ罪状であっても弁護士を付けるか否かによって、その後の処罰が変わってくる実態に気付かされます。
また飲酒運転による人身事故などを起こした場合は、民事・刑事・行政という3つの責任を負う必要が出てきますので、何の法律知識も持たない人が自分で全てを解決するためには相当の労力が必要になってくると言えるでしょう。
今回は、飲酒運転の基礎知識と、逮捕後に早期釈放や不起訴といった結果を求めて弁護士を雇うメリットについて詳しく解説していきます。
飲酒運転とは?
飲酒によってアルコールの影響が生じる状態で、自動車などの車両を運転することを、飲酒運転と呼びます。
ちなみに同様の状況下で航空機や船舶などを操縦する場合は、飲酒操縦という言葉が使われるようです。
交通法規による規制では、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」という2つのカテゴリで、刑事罰などを定めています。
酒気帯び運転
血液1mlにつき0.3mg以上もしくは呼気1リットルにつき0.15ml以上のアルコールを体に含んだ状態で運転することを、酒気帯び運転と呼びます。
酒気帯び運転のみの違反行為で逮捕された場合、13点の基礎点数が加算される仕組みです。
また酒気帯び運転に速度超過や積載物重量制限超過、無免許運転といった違反行為がプラスされた場合は、最大で25点もの点数になってしまうケースもあります。
酒酔い運転
これに対して酒酔い運転は、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場合」に運転した時に該当するカテゴリです。
酒酔い運転で逮捕された場合は、他の違反行為がなくても35点もの基礎点数になってしまいます。
こうした場合は即座に免許が取り消しになりますので、注意が必要です。
また累積点数が35点になった場合は、前歴のない人であっても最低3年の欠格期間により長きに渡って運転免許の再取得ができない形になります。
また特定違反行為による処分の場合、欠格期間が最長10年になることもありますので、仕事や日々の生活に運転免許が必要不可欠といった方々にとっては、酒酔い運転による行政処分のペナルティはかなり大きいと捉えて良さそうです。
「正常に運転できないおそれ」はどのように決まるの?
酒酔い運転の基準となる「正常に運転できないおそれ」は、「ろれつが回っているか?」、「手に震えはないか?」、「まっすぐ歩けるか?」といった状況から個別に判断される仕組みです。
お酒の強さに個人差があることから、「正常に運転できないおそれ」には、体内に含まれるアルコール量では一律な判断が行われない形となるようです。
飲酒運転に関する刑罰の種類とは?

飲酒運転による刑事罰には、非常にたくさんの項目が存在しています。
運転者の刑罰
運転者自身の刑事罰については、前述の酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分けられます。どちらかと言えば軽い位置づけとなる酒気帯び運転の刑罰は、50万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役になる形です。これに対して酒酔い運転で逮捕された時には、100万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役という刑事罰が課せられます。
同乗者の刑罰
運転者が飲酒運転をしていることを知っているのに、自分の運送を依頼・要求した場合に、同乗者にも飲酒運転の刑事罰が課せられる形となります。
具体的な刑罰は、酒気帯び運転で30万円以下の罰金もしくは2年以下の懲役、酒酔い運転で50万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役になる仕組みです。
こうした形で同乗者にも刑罰が設けられている実態から考えると、飲酒運転を行おうとする運転者に対して、同乗者を含めた周囲の方々も運転代行の利用などを勧める心掛けが必要だと言えるでしょう。
飲酒運転で人身事故を起こした場合の刑罰
飲酒運転によって歩行者をひいてしまった、前方を走る車に衝突して相手にケガをさせてしまったなどの人身事故があった場合、かなり厳しい刑事罰が課せられる形となります。
例えば、このカテゴリで最も軽い酒気帯び運転であっても、懲役刑の最長は10年、罰金刑は最大150万円になる仕組みです。
これに対してアルコールの影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる「めいてい運転」だった場合は、その行為が故意か否かによって刑罰が大きく変わる形です。
めいていの故意がある状況下で負傷事故を起こした場合は懲役の最長は15年、被害者が亡くなってしまった時には最長20年の懲役刑になるようです。
飲酒運転による人身事故の現場から逃げた場合
例えば、お酒を飲んだ状態で人身事故を起こした加害者が、飲酒運転の発覚から逃れるために現場から逃げた場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪により懲役1年~12年の罪が課せられます。
また事故を起こした後に更にアルコールを飲んだ場合も、発覚免脱罪が成立する形となるため、飲酒運転による人身事故後の行動には注意が必要だと言えるでしょう。
飲酒運転により刑務所に入ることはあるの?
飲酒運転で逮捕された場合に刑務所に入るか否かという判断は、その罪の重さによって変わってくると考えられます。
例えば、深夜の検問で酒気帯び運転の事実が発覚した場合は、その場で逮捕されても勾留には至らず、釈放されるケースがほとんどです。
これに対して明らかに悪質とも言える重傷事故や酩酊運転による人身事故を起こした場合は、勾留される可能性が高まると捉えて良いでしょう。
飲酒運転における刑事処分

飲酒運転を起こした人の刑事処分は、人身事故か否かによって大きくその後の状況が変わってくる実態があります。
人身事故を伴わないケース
酒気帯び運転で逮捕された人が初犯だった場合は、略式裁判により罰金刑になるケースが多いです。
これに対して酒酔い運転の場合は、公判請求から正式裁判へと移り、懲役刑を請求される可能性が高まる実態があるようです。
初犯の場合は執行猶予がつくのが一般的となりますが、その期間内に再び飲酒運転を行った時には、実刑判決になると捉えた方が良いでしょう。
人身事故を伴うケース
これに対して被害者に死傷を負わせた人身事故の場合は、相手方のケガの程度が軽く示談成立している時に略式裁判から罰金刑という流れになるようです。
しかし通常は公判請求される形となるため、注意が必要です。
執行猶予期間中に人身事故を伴う飲酒運転を行った場合は、被害結果が重大であったり、事故の態様が極めて悪質と判断された場合は、実刑判決になることもあります。
これに対して、それ以外のケースにおいては弁護活動によって執行猶予を獲得できる可能性もあるようです。
飲酒運転で逮捕された時には弁護士にサポートを仰ぐのがおすすめ
こうした形で刑事処分におけるパターンが非常に細かい飲酒運転で逮捕された場合は、起訴前に「早期釈放の実現」と「不起訴処分の獲得」のために、弁護士を雇う方法がおすすめとなります。
早期釈放の実現
早期釈放に実現に向けて弁護士が行える活動は、下記の3つとなります。
・検察官への勾留請求しない求め
・裁判官に勾留決定をしない求め
・裁判官に裁判所が行った勾留決定を取り消す求め
こうした弁護活動は、飲酒運転を行ってしまった当事者の家族などにはできない手続きです。
また飲酒運転による逮捕で取り調べが行なわれた後は、非常にスピーディーに手続きが行われる形となりますので、こうした流れを全て把握する弁護士のお世話になるのが理想と考えて良いでしょう。
不起訴処分の獲得
弁護士による弁護活動によって無罪(不起訴)もしくは執行猶予という結果に至れば、飲酒運転を起こした本人は刑務所に入らなくてよくなります。
特に飲酒運転の結果として人を死傷させてしまった場合は、実刑判決によって刑務所行きになる可能性も出てきますので、弁護士による実刑を回避するための活動は今後の人生といった長いスパンで考えても必要不可欠なことであると言えるでしょう。
被害者との示談交渉
実刑判決の回避には、被害者との示談交渉による和解が大変重要なポイントとなります。
例えば、弁護活動により慰謝料などの折り合いがつき、示談が成立すれば、当事者間での問題解決が概ね図られたという意味により、裁判所による量刑判断に影響する仕組みです。
しかし飲酒運転による逮捕によって身柄拘束されてしまった場合は、被害者との接触ができないことにより示談交渉が難しくなりますので、加害者が拘置所にいる間は弁護士によるサポートはやはり必要不可欠と捉えた方が良いでしょう。
また弁護士は交通事故トラブルにおける示談交渉のスペシャリストとも言われていますので、飲酒運転以外の事故においても相手方との話し合いをお願いするメリットは非常に高いと捉えて良いでしょう。
飲酒運転で弁護士を雇う理想的なタイミングとは?
飲酒運転事故で早期釈放を目指すなら、勾留が確定する前、逮捕から48時間以内に弁護士を雇うのがベストのタイミングと考えられます。
また勾留が確定してしまうと最低10日は身柄拘束される形となりますので、その後の日常生活に支障をきたいさないためにも、なるべく事故を起こした本人の家族は早めに弁護士を雇う方向で動く必要があると言えるでしょう。
交通事故
に強い